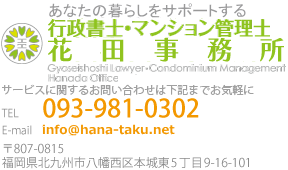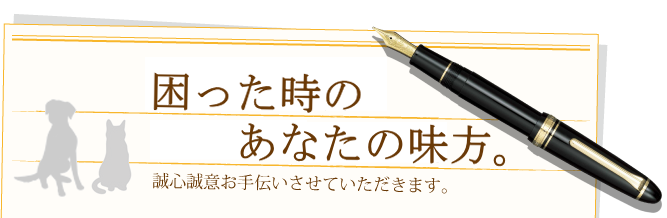- 「遺言書」と「契約書」
実物のサイズはA5
色はモノクロです
ペットに遺産は残せない?
最近では「遺言書」も随分世間に浸透してきたように思います。
ひとむかし前までは「遺言書を作るなんて縁起が悪い」
なんていう偏見を持った方も多かったようですが、
今ではそんなことを言っていたら勉強不足を笑われるそうです。
「遺言書」というのは人間がこの世界に残す最後の意思表示です。
その効果が発揮されるのは、「遺言書」を作った人間が亡くなった時です。
そこで、この「遺言書」を利用して、あなたの大切なペットの世話をしてもらいましょう。
"私の財産のうち1千万円を、私の愛犬ポチに遺す"
「こう遺言書に書いておけば、ポチの世話を喜んでする人間がいるはず。だから安心、安心」
残念ながらこれでは安心できません。
日本の法律では、ペットなどの動物に直接、財産を残すことはできないのです。
「負担付遺贈」
だったらどうすればいいのでしょうか?
"直接"財産を残せないのであれば"間接"的に財産を残せばいいのです。
それが「負担付遺贈」という方法です。
誰か人間に財産を遺す代わりに、その条件(負担)としてペットの世話をしてもらうのです。
例えば、
"○○に1千万円を遺贈する。ただし、その負担として愛犬ポチの世話をしなければならない"
このようにです。
念には念をいれておくのが当然
遺言書で「負担付遺贈」をしておけば、ひとまずあなたのペットも安心です。
しかし、大切なペットの"命"に関することです。
ペットは人間と違って言葉で訴えることができません。
あなたの遺言書どおりに世話をしてもらえなくても、声を上げることができないのです。
念には念を入れておく必要があります。
そこで、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておきましょう。
「遺言執行者」とは、遺言書の内容が正しく実現することを任務とする人です。
未成年者や破産者でない限り「遺言執行者」には誰でもなることができますが、
基本的には、利害関係のない第三者(行政書士など)に依頼しておくのがいいでしょう。
注意点
「遺言書」ですからその名の通り「書面」でなくてはなりません。
「音声レコーダー」や「ビデオ映像」では、民法上、法的な効果を発揮できません。
さらに「遺言書」は、あなたが単独でできる一方的な意思表示ですので、
遺言書で財産をもらう人が「財産なんていらな~い。だからペットの世話もしな~い」
と言って、財産をもらう権利を放棄すると同時に、ペットの世話もしないとすることも自由です。
そうならないためにも、事前に誰に頼むのが良いのかよく考え、
その人にきちんと話しをしておく必要があるのかもしれません。
もうひとつ「負担付死因贈与契約」という「契約書」を作成しておく方法もあります。
その方法についてはこちらのページへ⇒契約書について
ご依頼はこちらから
「ペットの為に何か残さなくてはいけない!」
そう感じていただけた方は、下記のいずれかで行政書士花田事務所へご依頼ください。
電 話 093-981-0302
FAX 093-601-7845
メール info@hana-taku.net
ペット遺言専用ページ⇒『ペットの為の遺言書・契約書お申込みフォーム』